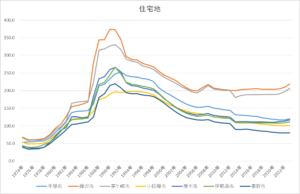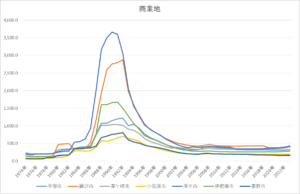住宅地と商業地の地価調査の平均価格です。
神奈川県オープンデータカタログサイトの神奈川県地価調査平均価格・平均変動率推移表の神奈川県地価調査平均価格を利用しています。
1974年(昭和49年)から2023年(令和5年)までのデータがあります。
単位は、「千円/㎡」です。
元データは、以前に記した「地価(平均価格、住宅地)」「地価(平均価格、商業地)」と同じになりそうです。
ただ、新型コロナウイルス感染症が拡大し、沈静化していった期間が含まれているため、改めて確認しました。
住宅地です。
(出典:神奈川県オープンデータカタログサイトの神奈川県地価調査平均価格・平均変動率推移表)
商業地です。
(出典:神奈川県オープンデータカタログサイトの神奈川県地価調査平均価格・平均変動率推移表)
2019年(令和元年)までのトレンドは、「地価(平均価格、住宅地)」「地価(平均価格、商業地)」に記した通りです。
いわゆるバブルの時期に高騰し、その後は低下傾向にありますが、持ち直しが見られるところもあります。
住宅地では藤沢市と茅ヶ崎市の2市が、商業地では藤沢市、厚木市、茅ヶ崎市が比較的高い水準にあります。
平塚市は、全体ではいずれも平均的です。
新型コロナウイルス感染症の影響があった2020年(令和2年)以降も、市による違いが表れていました。
コロナ前の2019年(令和元年)とコロナ後の2023年(令和5年)を比較します。
住宅地は、7市中5市で2023年の地価が2019年を上回っています。
中でも、藤沢市と茅ヶ崎市は、10%以上の高い伸びを見せています。
住宅地としてより一層、人気が高まったようです。
商業地は、7市中4市で2023年の地価が2019年を上回っています。
中でも、藤沢市、厚木市、茅ヶ崎市は、5~9%台の伸びを見せています。
平塚市は、住宅地では103.68%、商業地では99.09%の伸びでした。
住宅地の地価はコロナ前より上がったものの、他市に比べると比較的緩やかなようです。
商業地は、魅力の高まりが弱いというか、低下傾向から脱し切れていないように見えました。